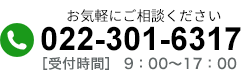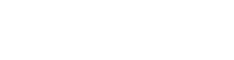お知らせ・コラム
【相続資産】意外な相続資産を分かりやすく解説
相続財産というと一般的には現預金や不動産、貴金属など、お金になるものを受け取るイメージが多いかと思います。しかし、相続というのは上記のようなプラスのものだけでなく、借金等のマイナスの物も対象になります。そういったプラスの財産を積極財産、マイナスの財産を消極財産と呼び、また被相続人(亡くなった方)の持ち物であっても、相続できないものもあります。今回はその中でも少し意外な遺産の具体例をご紹介したいと思います。
相続資産一覧
まず、相続資産を一覧にすると以下のようになります。
| プラスの資産(積極資産) | マイナスの資産(消極資産) | 相続財産とみなされないもの | |||
| 現物資産 | 現金・預貯金等 | 負債 | 借金・ローン等 | 祭祀財産 | 墓地・仏壇・位牌等 |
| 不動産 | 土地・家屋 | 保証債務 | 原則として相続 | 香典・葬式費用 | |
| 不動産上の権利 | 借地権・抵当権等 | 損害賠償債務 | 不法行為・債務不履行 | 生命保険金 | 故人以外が受取人のもの |
| 動産 | 自動車・貴金属等 | 公租公課 | 未納の税金等 | 死亡退職金・葬祭費・埋葬料 | |
| 有価証券 | 株式・公社債等 | 買掛金 | 営業上の未払代金 | その他 | 故人にのみ帰属する権利 |
| その他債権 | 売掛金・貸付金等 | ||||
| 知的財産権 | 著作権等 | ||||
| 生命保険金 | 故人が受取人のもの | ||||
| その他 | 還付金・給付金等 | ||||
預貯金
現物資産と呼ばれる預貯金ですが、内容によっては相続の税額を大きく左右させるものがあります。特に代表的なのが、「名義預金」です。名義預金とは相続において、亡くなった方が配偶者・子供・孫の名義で財産を残しているものを指します。しかし、配偶者・子供・孫等の名義で預金されていても、それが形式的なものであって、実質的には相続人の物であると判断されるものは相続資産として申告する必要があります。名義預金は名義の名前と本当の持ち主が違うことから、被相続人の財産から漏れやすく、税務調査で指摘が多い財産です。また、預貯金は生前に名義を安易に変更することができるため、相続財産を減らすための対策として家族名義の相続財産がないか、調査官は預貯金の動きも含めて入念にチェックします。(通常相続発生前5年~10年)
名義預金として指摘されない様、現預金には贈与等の事前の対策をしっかり行いましょう。
知的財産権
知的財産権を代表するものと言えば、著作権です。著作権とは、著作物(音楽・小説・ソフトウェア等)を創作した著作者に与えられる権利の総称です。著作権は「権利の束」と表現されることがあります。それは「著作権」という名称の単体の権利があるというよりかは、様々な種類の権利が集まったものが「著作権」と称されるからです。
原則的に、著作権に含まれる権利は著作権法に規定されています。その種類は「著作者人格権」と「著作財産権」に分けることができます。(以下表参照)
①著作者人格権
| 公表権 | 著作物を公表するか否か等を決定する権利 |
| 氏名表示権 | 著作物を公表する際に著作者名を表示するか否かを決定する権利 |
| 同一性保持権 | 著作物やそのタイトルを意に反して改変されない権利 |
| 名誉声望保持権 | 著作者の声望や名声を害する方法によって著作物を利用されない権利 |
| 複製権 | 著作物を印刷・写真撮影、コピー機による複写などで著作物を複製する権利 |
| 上演権・演奏権 | 演劇のように、著作物を多くの人に見せたり聴かせたりする権利 |
| 上映権 | DVDなどで収録された著作物(絵画、映画、写真等)を、多くの人に見せるために上映する権利 |
| 公衆送信権 | 著作物を公衆に送信する権利 |
| 公の伝達権 | 著作物を公衆に伝達する権利 |
| 口述権 | 著作物を朗読などで多くの人に伝える権利 |
| 展示権 | 著作物を多くの人に見てもらうために展示する権利 |
| 頒布権 | 劇場型映画などを販売したり、貸したりする権利 |
| 譲渡権 | 映画以外の著作物やその複製物を多くの人へ貸出する権利 |
| 貸与権 | 映画以外の著作物やその複製物を多くの人に貸し出しする権利 |
| 翻訳権・翻案権 | 著作物を翻訳、翻案などを施し、二次的著作物を制作する権利 |
| 二次的著作物の利用権 | 自分の著作物を原作とする二次的著作物の利用について原作者が持つ権利 |
香典
香典には相続の対象に含まれません。基本的に参列者から供えられた香典は喪主が受け取り、葬式費用の一部となることが多く、喪主への贈与とみなされます。相続税に関する規定において、香典やご祝儀といったお金は基本的に非課税と定められているため、香典には相続税も贈与税も発生しません。また非課税所得の扱いとなるため、確定申告の際に申告する必要もありません。しかし、香典の総額が社会通念上きわめて高額だった場合、相続税法により、贈与税の課税対象になる場合もあるので注意が必要です。
故人にのみ帰属する権利
故人にのみ帰属する権利とは、一身専属権を指します。一身専属権とは、個人の人格や才能、あるいは個人としての法的地位などとの間に密接不可分の関係にあるために、他人による権利行使を認めることができない権利義務です。一身専属権としては以下のような権利が挙げられます。| 身分法上の権利 | 扶養請求権、婚姻費用分担請求権、離婚請求権、認知請求権等 |
| 人格権 | 著作者人格権 |
| 故人の信頼関係に基づく権利 | 代理権(本人に代わって意思表示を行うこと。) |
| 不代替的給付に関する権利 | 雇用契約上の権利 |
| 人的色彩の強い団体構成員たる地位 | 組合契約における組合員の地位 |
| 社会保障上の権利 | 生活保護、各種年金受給権等 |
最後に
ここまで様々な相続資産をご紹介いたしました。相続資産というのは、その人それぞれの状況で相続資産扱いになったりならなかったり変化することが多く、またその内容次第では、相続税の金額が大きく変わってしまいます。相続税の判断には、総合的に勘案して検討することが必要です。
その為、税理士をはじめとした経験豊富な専門家とご相談のうえで申告されることをお勧めいたします。
影山タックスパートナーズでは開業以来、地元仙台を初めとして県外のお客様からも選ばれている実績を持ち、相続のプロが遺産分割の手続きから相続税の申告まで様々なサポートを行っています。
相続でお悩みの際は、ぜひお気軽に影山タックスパートナーズにご相談ください。
ご相談・お問い合わせ

- 全国対応
- ご相談無料
- お気軽にご相談ください
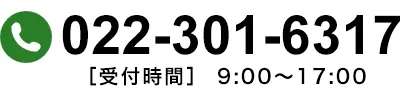
- メールでのお問い合わせ24時間受付