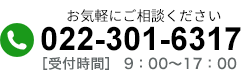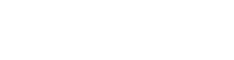お知らせ・コラム
【書類の山から解放されませんか?】ペーパーレス化を進めましょう!

昨今、さまざまな分野でペーパーレス化が進み、紙を使わなくとも電子データのやり取りだけで取引や手続きが完結することも増えてきました。
しかし、経理や人事労務、総務といったバックオフィス業務では、まだまだ紙でのやり取りも多いのが実情ではないでしょうか。
今回は、
- ペーパーレス化のメリット
- どのようにペーパーレス化を進めるか
- 電子帳簿保存法への対応
ペーパーレス化のメリット
ペーパーレス化のメリットとして、- 業務効率化
- 経費削減
- 情報漏えい、文書紛失リスク低減
- リモートワーク対応
- 災害対策
業務効率化
例えば紙文書をスキャンし、PDFなどのデジタルデータにすることで容易に管理や検索ができるようになります。膨大な書類を保管・管理をする手間や書類の山の中から必要な文書を探す時間が省け、業務の効率化につながります。
経費削減
紙文書で業務を行う場合、用紙代、印刷代、印刷機器の費用(リース代やトナー代、メンテナンス費用等)、郵送代、廃棄費用、保管スペース費用など多額のコストがかかります。もちろん全てを0にすることはできませんが、ペーパーレス化を図ることで、こうした費用を多少なりとも圧縮し、経費削減につなげることができます。
情報漏えい、文書紛失リスク低減
紙文書の場合は、鍵付きのキャビネットで保管するなど物理的なセキュリティ対策しかできませんが、デジタルデータであれば、アクセス権限や閲覧制限を設定し、情報漏えいを防ぐことができます。また、クラウドサービス等では、閲覧や編集のログを記録することができるため、文書の不正な持ち出しや改ざん、紛失といったリスクに対応することができます。
リモートワーク対応
新型コロナウイルスの影響で急速に広まったリモートワーク。しかし、紙文書での業務がリモートワークを導入するうえで支障の1つになっています。ペーパーレス化を図ることで、どこからでも文書を閲覧・編集できるようになるため、場所を問わず業務を行う体制を整えることができます。
災害対策
地震や大型台風、豪雨など多くの災害が発生する中、紙文書の保管は紛失や破損といったリスクを抱えることになります。文書データをクラウドサービスなどに保管しておけば、万が一の際にも速やかに復旧することができ、事業の継続性を高めることができます。
ペーパーレス化を進めるために・・・

では、どのようにペーパーレス化を進めていけば良いのでしょうか?順を追って解説していきます。
紙文書を使っている業務の洗い出し
まずは業務全体を確認し、紙文書を用いている業務をピックアップしていきます。その際に誰が、どのような目的で紙を用いているのかを把握していきましょう。
ペーパーレス化が可能か検討する
洗い出した業務や紙文書の中でペーパーレス化が可能なものが無いか検討していきます。取引先や顧客、法令等の関係で、どうしてもペーパーレス化ができないもの以外は一度検討し、優先順位を付けていきましょう。
デジタルツールを導入する
ペーパーレス化を図るために欠かせないのは、デジタルツールの活用です。近年はさまざまなデジタルツールが登場していますが、用途や目的にあったツールを選択し、導入していくことが大切です。
また、情報漏えいやデータの紛失を防ぐため、セキュリティ対策も同時に考えていく必要があります。
業務フローの整備、取引先・顧客への説明
ペーパーレス化を図ることで、既存の業務フローを見直す必要が生じることも多々あります。例えば、これまで印鑑やサインといった形で決裁していたものを電子決裁へ切り替える、従業員の経費精算をシステムを通して行う、といったことが挙げられます。
また、請求書や契約書など書類を電子データでのやり取りで行いたい場合は、取引先や顧客へあらかじめ説明を行う必要も生じるでしょう。
社内教育・フォロー体制の整備
ペーパーレス化を図ることで、新たなツールの導入や業務フローの変更など多くの変化を伴うことになります。特に、これまで紙文書中心で業務を進めてきた従業員やデジタルツールに慣れていない従業員は、大きな抵抗感を感じるかもしれません。
しっかりと目的やメリット、効果を周知し、マニュアル整備や研修などのフォローを行うことが大切です。
電子帳簿保存法への対応
企業におけるペーパーレス化に対応するため、国では電子帳簿保存法(電帳法)を定め、帳簿や書類等の電子データでの保管を認めています。直近では、2022年1月に改正が行われ、要件が緩和される一方、規制や罰則も強化されました。
同法では、帳簿書類データの保存区分を、①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存の3種類に分けています。
このうち、③電子取引データ保存については、2022年1月以降、義務化されています(2年間の猶予期間あり)。
①電子帳簿等保存は、「電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存」することです。
具体的には、会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類などを「電子データのまま保存する」ことです。
具体的には、会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類などを「電子データのまま保存する」ことです。
②スキャナ保存は、「紙で受領・作成した書類を画像データで保存」することです。
具体的には、取引先等から受け取った請求書や領収書などをスキャンしてデータ化し、保存することです。
具体的には、取引先等から受け取った請求書や領収書などをスキャンしてデータ化し、保存することです。
③電子取引データ保存は、「電子的に授受した取引情報をデータで保存」することです。
具体的には、領収書や請求書などをデータでやりとりした場合には「電子取引」に該当し、そのデータを保存しなければならないというものです。
これは、「ネット通販なら必ずデータ保存が必要」というわけではなく、あくまで領収書などを紙ではなくデータで受け取った場合等だけが対象です。具体的には、領収書や請求書などをデータでやりとりした場合には「電子取引」に該当し、そのデータを保存しなければならないというものです。
これまでは電子データを出力した紙で保存しても良かったのですが、今後は、オリジナルの電子データの状態で保存しておく必要があります。
※2023年12月末までの2年間に行われた取引は、いままでどおり出力した紙を保存することも可能です。
| 保存区分 | 概要 |
|---|---|
| ①電子帳簿等保存 | 電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存 |
| ②スキャナ保存 | 紙で受領・作成した書類を画像データで保存 |
| ③電子取引データ保存 | 電子的に授受した取引情報をデータで保存 |
電子取引データ保存については、2年間の猶予期間が設けられているとはいえ、2023年12月末までには、対応できるようにしておかなければないため、今のうちから準備を進めることが必要です。
※電子取引データ保存についてはこちらの記事もご覧ください。
~令和4年1月から義務化~電子帳簿保存法の電子取引保存を解説!無料で、簡単な運用方法をご紹介!
まとめ
- ペーパーレス化には、業務効率化、経費削減、情報漏えい、文書紛失リスク低減、リモートワーク対応、災害対策など多くのメリットがある。
- ペーパーレス化を進めるためには、業務の洗い出しや選定、デジタルツールの導入、業務フローや社内体制の整備などが必要になる。
- 電子帳簿保存法に対応するためにも、早めにペーパーレス化を進めることが望ましい。
ペーパーレス化は社内外さまざまなところに影響を及ぼすため、一朝一夕に進むものではありません。
しかし、世の中のペーパーレス化がますます進む中、対応が遅れることは大きなリスクとなる可能性もあります。
まずは業務を1つ1つ見直し、出来るところから始めてみてはいかがでしょうか?
弊社でも現在、ペーパーレス化に積極的に取り組んでおります。
「ペーパーレス化を進めたいが何から始めたら良いか分からない」「どのようなデジタルツールを導入したら良いか分からない」などといった、疑問やご質問にも担当スタッフがお答えします。
また、デジタルツール等を活用した業務改善の支援として、IT顧問サービスもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
IT顧問サービスについて
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
ご相談・お問い合わせ

- 全国対応
- ご相談無料
- お気軽にご相談ください
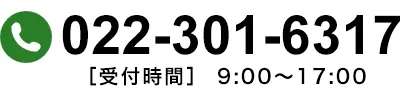
- メールでのお問い合わせ24時間受付