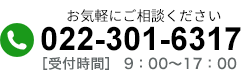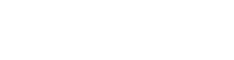お知らせ・コラム
【相続発生の手続きについて】身近な人が亡くなった時の手続きを分かりやすく紹介
身近な人が亡くなるというのは大きな悲しみです。しかし、自分が相続人という立場であれば、遺産相続という大きな問題に直面することになるでしょう。
相続手続きは何度も経験するものではありません。その為、どんな手続きがいつ必要なのか、わからないことが多く不安に感じる方が多いと思います。
そんな方々のために、ここでは身近な人が亡くなったら何から始めたらいいか、相続開始から相続税申告までの大まかな流れをわかりやすく説明いたします。
相続財産について
まず、相続するものが一切なければ、相続手続きは必要ありません。しかし「相続をするものが一切ない」という状況はあまりなく、把握していないだけで、相続財産は何かしらあるというケースがほとんどです。(下記表参照)| プラスの資産 | マイナスの資産 | ||
| 現物資産 | 現金・預貯金等 | 負債 | 借金・ローン等 |
| 不動産 | 土地・家屋 | 保証債務 | 原則として相続 |
| 不動産上の権利 | 借地権・抵当権等 | 損害賠償債務 | 不法行為・債務不履行 |
| 動産 | 自動車・貴金属等 | 公租公課 | 未納の税金等 |
| 有価証券 | 株式・公社債等 | 買掛金 | 営業上の未払代金 |
| その他債権 | 売掛金・貸付金等 | ||
| 知的財産権 | 著作権等 | ||
| 生命保険金 | 故人が受取人のもの | ||
| その他 | 還付金・給付金等 | ||
| 相続財産とみなされないもの | |
| 祭祀財産 | 墓地・仏壇・位牌等 |
| 香典・葬式費用 | |
| 生命保険金 | 故人以外が受取人のもの |
| 死亡退職金・葬祭費・埋葬料 | |
| その他 | 故人にのみ帰属する権利 |
何もないと思っていたら予想外の資産(預金口座・不動産)や負債(借金・未払金)があり、税金がかかってしまった・知らずに借金を背負ってしまったということにならない様、念のため確認するということがとても重要になります。
遺産相続の手続きの流れ
相続の開始から相続税申告までの流れは図に表すと以下のようになります。.png)
死亡届の提出
まず最初に提出することになるのが死亡届です。死亡届とは、人が亡くなった事実を公的に証明する書類です。以下の届出義務者は、死亡の事実を知った時から7日以内に届け出なければならないと定められています。死亡届の提出義務者(順位)
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主・地主または家屋もしくは土地の管理人
死亡届には、死亡診断書または検案書を添付しなければいけないと定められています(戸籍法第86条2項)。
病院の入院中に亡くなられた場合は入院している病院で死亡診断書を出してもらえます。また自宅で亡くなられた場合、持病があって通院されていた場合は、その掛かっていた病院に連絡すると、死亡診断書を出してもらえます。
持病もなく通院しておらず、自宅で亡くなられた場合は、住んでいる地域所轄の警察署に連絡しましょう。その後、警察の方が死体検案書を発行してくれます。これは医師が診断した病気以外で亡くなられた時にも発行される公的書類になります(例:がんを患い、がんで亡くなる=死亡診断書・骨折で入院して肺炎で亡くなる=死体検案書)
公的年金・健康保険・公共料金等の手続き
・国民年金、厚生年金国民年金の場合は亡くなった日から14日以内に、厚生年金の場合は亡くなってから10日以内に、年金事務所で年金受給停止手続きを行う必要があります。ですが、日本年金機構にマイナンバーを届け出ていた場合はこちらの手続きは不要になりますので、一度確認すると安心でしょう。
・健康保険
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されていた方は、亡くなった日から14日以内に市区町村へ保険証を返納します。被相続人が会社の健康保険に加入されている場合は、手続き方法を勤務先に確認する必要があるので注意が必要です。
・公共料金等
故人の口座は銀行が口座の持ち主の死亡を知った時点で凍結されます。そのため、公共料金等の引き落とし口座の変更が必要です。
また、パスポートは各都道府県の旅行事務所へ、運転免許証は警察か運転免許センターに返納しましょう。パスポートも運転免許証も返納はしても形見として手元に残すことができますので、希望する場合は返納の際に手元に残したい旨を伝えると良いでしょう。
・死亡保険金の請求手続き
被相続人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金の受け取りが発生する為、保険会社へ連絡をする必要があります。
相続人の調査
葬儀が終わる頃には、故人の戸籍や住民登録に関する手続きはだいたい終わっています。戸籍の手続きの次に重要なものが遺産相続に関する手続きです。遺産相続を始める前には必ず、相続人の人数と相続財産の内容を調査しなければなりません。相続人と相続財産をきちんと調べておかなければ、本来必要な手続きをしないなど手続きを誤る可能性があります。また、予期しない相続人が現れ泥沼に陥る可能性もありますので、慎重に行う必要があります。
相続人は戸籍謄本をもとに調査し、相続人になる人は、民法で順位が定められています。故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本をもとに、誰が相続人になるかを確認します。
民法における相続人の順位
・常に相続人:配偶者
・第1順位:子(子が死亡している場合は孫)
・第2順位:父母(父母が両方とも死亡している場合は祖父母)
・第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)
・常に相続人:配偶者
・第1順位:子(子が死亡している場合は孫)
・第2順位:父母(父母が両方とも死亡している場合は祖父母)
・第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)
.png)
兄弟姉妹が相続人になる場合は、故人の両親の出生から死亡まで連続した戸籍謄本も取り寄せて、他に兄弟姉妹がいないかも確認します。
相続人を調査した結果、隠し子や養子、前妻の子供など想定していない相続人が明らかになることもあります。想定外の相続人であっても、その人を除いて遺産相続の手続きを進めることはできませんので、注意が必要です。
相続財産の調査
相続人が決定した後は相続財産の内容を調査します。具体的には、どこにどれくらいの額があるかを確認する作業になります。この作業はスムーズに遺産相続を進め相続税を正確に申告するために必ず必要な調査です。申告漏れがあれば、税務調査を受けて相続税を追加徴収されるだけでなく、延滞税や過少申告加算税などが課される可能性もあります。また、借金や債務保証も遺産相続の対象に含まれますので、故人の借金を肩代わりしないように借金や債務保証の有無をしっかり調べておく必要があります。
また、調査の時に忘れてならないのが「遺言書」です。遺言書が遺されていないかどうかも一緒に調べる必要があります。
故人の遺言書が見つかった場合、遺言書を家庭裁判所に持ち込んで検認手続きをする必要があります。検認とは、遺言書が形式的な要件を満たしているかを確認し、偽造や変造を防ぐための手続きです。検認されていない遺言書は、相続手続きに使うことができませんので注意が必要です。
検認手続きは家庭裁判所に届け出てその日のうちに終わるものではなく、後日指定された検認期日に改めて家庭裁判所に行かなければなりません。検認期日まで1か月以上かかることもあるため、できるだけ早く手続きをするのがおすすめです。
ですが、遺言書が公正証書であった場合は検認の必要はありません。また2020年7月10日からは遺言書を法務局で保管できる制度が始まりました。法務局で保管された遺言書も検認は不要ですので、遺言書を見つけたときは一度確認してみてください。
遺産分割協議で遺産の分け方を決める
故人の遺産は、遺言書がある場合は遺言書の通りに分け合いますが、遺言書がなかった場合は相続人同士で話し合って分け合います。その遺産の分け方を決める話し合いを遺産分割協議といいます。遺産の分け方を決めるときは、民法で定める法定相続分を参考にすることが多いです。必ずこのとおりに遺産を分けなければならないというものではありませんが、話し合いがまとまらない場合は法定相続分で遺産を分けることになります。
| 相続人 | 法定相続分 |
| 配偶者と子 | 配偶者:1/2 子:1/2(複数いれば人数で均等に分ける) |
| 配偶者と父母 | 配偶者:2/3 父母:1/3(複数いれば人数で均等に分ける) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4(複数いれば人数で均等に分ける) |
遺産分割協議がまとまれば、その内容を遺産分割協議書に記録し、相続人全員の実印を押印して遺産分割の内容に合意したことを証明します。遺産分割協議書は遺産相続のあらゆる手続きで必要になるため、必ずやる必要のある手続きになります。
相続税の申告
遺産の総額が基礎控除額と呼ばれる一定の金額を超える場合は相続税を申告しなければなりません。基礎控除額は、以下のとおり3,000万円を基礎として相続人の数に応じて増えていきます。
相続税の基礎控除:3000万+600万×相続人の数(相続放棄した人も含む)
相続税の申告期限は相続の開始(故人の死亡日)の翌日から10か月以内です。
続税の申告書は自分で作成することもできますが、申告に必要な遺産価値の評価や税制上の特例の適用については専門知識が欠かせません。思わぬ申告漏れで過少申告加算税や、税務調査を受けて相続税の追加徴収されることのないよう、相続税の申告書は税理士に作成してもらうことをおすすめします。
最後に
ここまで相続税申告までの大まかな流れをご紹介いたしました。しかし相続というのは、その人それぞれの状況で必要な手続きや相続税の金額が大きく変わってしまいます。相続税の判断には、総合的に勘案して検討することが必要です。
その為、税理士をはじめとした経験豊富な専門家とご相談のうえで申告されることをお勧めいたします。
影山タックスパートナーズでは開業以来、地元仙台を初めとして県外のお客様からも選ばれている実績を持ち、相続のプロが遺産分割の手続きから相続税の申告まで様々なサポートを行っています。
相続でお悩みの際は、ぜひお気軽に影山タックスパートナーズにご相談ください。
免責事項
※当コラム内容は記事執筆時点の法令に基づいて作成しております。
※当コラムは執筆者の私見を含みます。正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
※当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
ご相談・お問い合わせ

- 全国対応
- ご相談無料
- お気軽にご相談ください
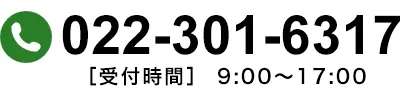
- メールでのお問い合わせ24時間受付