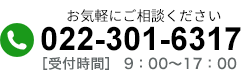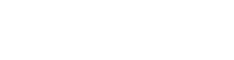お知らせ・コラム
旅費規程作成のポイント
出張手当を非課税にする!中小企業が絶対作るべき「旅費規程」
経営者の皆様、出張に伴う宿泊費や日当、交通費は正しく経費にできていますか?これらの費用を経費に計上する際、税務調査で否認されないために不可欠なのが「旅費規程」です。これをうまく活用すれば、従業員や役員に支払う出張手当を非課税にでき、会社も個人も大きなメリットを享受できます。
旅費規程とは何か?
旅費規程とは、会社が従業員や役員に出張を命じた際に支払う、旅費、日当、宿泊費などに関するルールを定めた社内規程です。この規程で定められた金額の範囲内で、社会通念上相当と認められる金額であれば、所得税が非課税になります。また、会社側もこれらの費用を損金(経費)として計上できます。
これは税法上の特例であり、給与として課税されることなく、実質的な手当を支給できる非常に有効な手段です。
なぜ旅費規程が必要なのか?
旅費規程がないと、出張費の精算は実費精算が基本となります。領収書を一枚一枚集めて精算する手間がかかるだけでなく、出張手当として支払った日当は給与と見なされ、課税対象になるリスクがあります。
一方、旅費規程があれば、以下のメリットを享受できます。
・節税効果: 役員や従業員に支払う日当が非課税となるため、個人は手取りが増え、会社は社会保険料や源泉所得税の負担を軽減できます。
・経費精算の簡略化: 出張のたびに領収書を精査する手間がなくなり、事務作業が大幅に効率化されます。
・公平性の確保: 役職や出張先に応じた手当の金額を明確にすることで、従業員間の不公平感をなくし、会社の公平性を保てます。
旅費規程を有効活用するポイント
有効な旅費規程を作るには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
1.出張の定義を明確にする
・ポイント: 「出張とは、会社から○km以上離れた場所への移動を伴う業務」など、出張と日帰り業務を区別する明確な基準を設けます。
・実務例: 「片道100km以上の移動を伴う業務」と定義することで、出張手当の支給対象を明確にします。
2.社会通念上相当な金額にする
・ポイント: 会社の規模や事業内容、出張先の相場を考慮した金額設定が重要です。高額すぎると給与とみなされるリスクがあります。
一般的な金額の目安
あくまで一般的な相場ですが、多くの企業では以下のような範囲で設定されています。この金額が絶対的な正解というわけではありませんが、一つの参考としてください。
参考
| 社長・役員 | 部長クラス | 一般社員 | |
| 国内出張(宿泊あり) | 6,000円 | 4,000円 | 2,500円 |
| 海外出張 | 10,000円 | 7,500円 | 5,500円 |
3.規程の整備と運用
ポイント: 旅費規程は、作成するだけでなく、社員に周知し、実際にその規程通りに運用することが不可欠です。
実務例: 規程を就業規則と一体化させるか、別規程として社員全員に配布・周知します。また、出張申請書や出張報告書を作成し、規程通りに手当が支払われているかを確認する体制を整えます。
税務調査で否認されないために
旅費規程があるからといって、必ずしも非課税になるわけではありません。税務調査では、以下の点が厳しくチェックされます。
規程の存在: 実際に旅費規程が存在し、法的な手続きを経て有効に成立しているか。
金額の妥当性: 設定された金額が社会通念上、高額すぎないか。
実態との整合性: 支払いの実態が規程通りに行われているか。
これらの点をクリアするために、作成した規程が形骸化しないよう、日々の運用が重要になります。
まとめ:旅費規程は会社の成長を支えるツール
旅費規程は、単なる事務手続きではありません。従業員のモチベーション向上、会社のキャッシュフロー改善、そして税務リスクの低減という、多角的なメリットをもたらす重要な経営ツールです。
「旅費規程をこれから作成したい」「今の規程が税務上大丈夫か確認したい」といったご相談は、ぜひ当事務所にお任せください。貴社の実情に合わせた最適な規程作成と運用をサポートいたします。
ご相談・お問い合わせ

- 全国対応
- ご相談無料
- お気軽にご相談ください
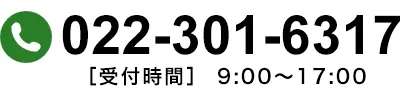
- メールでのお問い合わせ24時間受付