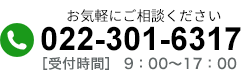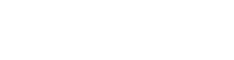お知らせ・コラム
令和7年税制改正のポイント解説:年末調整が変わる!総務・経理担当者が知っておくべきこと
令和7年度の税制改正により、年末調整の実務に大きな影響を与える変更が加わります。特に、基礎控除、給与所得控除、扶養控除の見直しは、多くの従業員の所得税額に直結するため、総務・経理担当者は正確な理解が求められます。本コラムでは、これらの変更点と、それに伴う年末調整の実務への影響を分かりやすく解説します。
1. 改正の背景:なぜ今、税制が変わるのか?
今回の税制改正は、主に以下の2つの背景に基づいています。- 物価上昇への対応 長らくデフレが続いていた日本経済は、近年、物価が上昇傾向にあります 。特に生活必需品を含む消費者物価は、平成7年から令和5年にかけて約20%上昇しています 。税の控除額が据え置かれると、物価が上がった分だけ実質的な税負担が増すため、家計の負担を軽減する必要がありました 。
- 人手不足と就業調整への対応 労働人口の減少が進む中、特にパートやアルバイトとして働く人々が、税や社会保険料の負担が増えないように、年収を一定額以下に抑える「年収の壁」が問題視されています 。今回の改正は、この「壁」を緩和し、より多くの人が働きやすい環境を整えることを目指しています 。
2. 基礎控除・給与所得控除・扶養控除の変更点
今回の改正では、給与所得者の税負担を軽減するため、以下のような措置が講じられます 。(1) 基礎控除の引き上げと上乗せ特例
これまでの基礎控除は、合計所得金額が2,400万円以下であれば一律48万円でしたが、改正後は最高額が58万円に引き上げられます 。さらに、低・中所得者層の負担に配慮し、給与収入に応じて控除額が上乗せされる特例が設けられます 。
- 給与収入200万円以下: 基礎控除58万円 + 上乗せ37万円 = 合計95万円の控除
- 給与収入475万円以下: 基礎控除58万円 + 上乗せ30万円 = 合計88万円の控除
- 給与収入665万円以下: 基礎控除58万円 + 上乗せ10万円 = 合計68万円の控除
- 給与収入850万円以下: 基礎控除58万円 + 上乗せ5万円 = 合計63万円の控除
(2) 給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得控除は、収入に応じて必要経費とみなされる控除で、最低額はこれまで55万円でした。 改正後は、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円になります 。これにより、年収162.5万円までの給与所得者は、給与所得控除が65万円となります。(3) 扶養親族等の所得要件の変更
今回の基礎控除の引き上げに伴い、扶養親族や同一生計配偶者と認められるための合計所得金額の要件も、48万円から58万円に引き上げられます 。これは給与収入に換算すると、年収103万円から123万円に引き上げられることになります 。これにより、これまで「103万円の壁」を意識して就業調整していたパートやアルバイトの年収が、123万円まで扶養の範囲内となります。
また、特定扶養控除の対象となる大学生年代の子(19歳以上23歳未満)についても、新たな特別控除が創設されます 。子の給与収入が150万円以下であれば、親は特定扶養控除と同額の63万円の所得控除を受けられます 。
3. 年末調整の実務における注意点
これらの改正は、令和7年12月に行われる年末調整から適用されます 。総務・経理担当者は、以下の点に注意して準備を進める必要があります。 ・扶養控除等申告書の変更 扶養親族の所得要件が変わるため、従業員に提出してもらう「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容を、新しい要件に沿って確認する必要があります。特にパートやアルバイトの配偶者を持つ従業員には、年収123万円まで扶養控除の対象となることを周知しましょう。
・システムへの対応 年末調整の計算を行う給与計算ソフトやシステムは、これらの改正に対応した更新が必要となります。令和7年12月の年末調整までに、システムのアップデートが完了しているか、ベンダーに確認しておきましょう。
・従業員への周知 今回の改正は、多くの従業員の所得税額に影響します。特に「年収の壁」を意識している従業員に対しては、新しい制度を分かりやすく説明し、不安なく働ける環境をサポートすることが大切です。
4. まとめ
令和7年税制改正は、基礎控除、給与所得控除等を大胆に見直すことで、物価上昇や人手不足といった社会課題に対応しようとするものです 。今回の変更は、年末調整の手続きに直接関わるため、総務・経理担当者にとって正確な知識が不可欠です。年末調整に向けて、国税庁や関連省庁の公式サイトで最新情報を確認し、自社の給与計算システムや従業員への周知体制を整えておくことで、スムーズな年末調整業務を実現しましょう。今回の改正を、従業員との信頼関係を深める良い機会と捉え、丁寧に説明していくことが求められます。
ご相談・お問い合わせ

- 全国対応
- ご相談無料
- お気軽にご相談ください
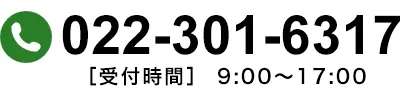
- メールでのお問い合わせ24時間受付